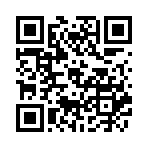2011年03月20日
【地震】東北地方太平洋沖地震7-6
2011年3月20日
「遠距離避難」
遠距離避難は、地震災害とそれに伴う津波災害の被災者に適するものではないです。
自然災害の被災者を避難所単位で受け入れようという動きがありますが、その後の
復旧や復興までを考えた時に、その避難所周辺の住民がゴッソリと居なくなって
しまうことになります。
物資や燃料が潤い出せば、復旧工事が始まり、直ぐに町の復興に繋がっていきます。
その繋がりを断ってしまうと修復には相当な時間を要してしまいます。
それならば、優先順位でご病気をされている方々や障害をお持ちの方々が避難することが
望ましいですね。
中越地震以降に要介護者、要援護者への避難所生活についてという話題があって
多くの自治体ではマニュアル化作業が進められているが、中越地震以前…古くは
正村が初めて参加をした雲仙普賢岳火山災害では、避難所生活に耐えられないと
判断した被災者は強制的に医療機関へ搬送されました。
北海道の有珠山でも痴呆が進んで糞尿を漏らしてしまわれる方を泣く泣く介護施設へ
運んだそうです。
実は中越地震以前は避難所生活に耐えられないと判断した被災者は強制的に該当機関
へ搬送されます。
避難所には比較的に元気な方だけが残ります。
感情的に言えば要介護者も要援護者も地域住民であり、一人も欠けることなく自治意識を
持って町の復興に…と言えますが、今回の地震や津波では、その考えの脆さを感じます。
自然災害の被災者を受け入れるより、今回の原発事故災害の被災者を引き受ける事を
考えたいです。
今後の復旧や復興を考えると他の自然災害での被災と違い、避難指示解除がなければ
復旧作業にも入れない原発避難者を受け入れる事が望ましいです。
文責:
災害OUT・SIDE
正村圭史郎
Email saigaioutside@yahoo.co.jp
Posted by すきまかぜ編集部 at
03:33
│Comments(0)
2011年03月20日
【地震】東北地方太平洋沖地震7-5
2011年3月20日
「遠距離避難」避難所と仮設住宅の運営を考える
避難所といえば救援物資の仕分けや被災者への救援活動に多くのボランティアが
活動を行うイメージですが、
この「遠距離避難」の避難所では、一般ボランティアの活動参加は無いものとします。
自治会組織を立ち上げていただき、掃除や食事の世話などは自治会の会合などで被災者の
皆さんが決めていただき行ってもらう。
避難所の管理責任は当該避難所として使用している体育館などの職員が担当するが、
避難者からも管理責任者から消灯などの作業を担うこともあります。
物資の仕分けや搬入などの作業は、雇用対策の一環として被災者が担えば生活再建の
一つの行動といえます。
避難所の自治に関する活動は、被災者自らが担う事が重要です。
それ以外の作業は…
医師、看護師、介護士などの有資格ボランティアが活動を行います。
避難所での運営には、自治会内で話し合い、自治会役員などと滋賀県や当該避難所の市町関係者
が参加をし会議を行う。
仮設住宅へは、避難所で構築された自治会組織の班単位で入居することが望ましいです。
個室内での新たなコミュニティー作りには個人差があります。また、コミュニティー作りに失敗
して塞込んだ場合に仮設内では発見が遅れることになります。
避難所や仮設住宅に一般ボランティアが参加したいと申し出や学生(生徒)などからも
希望者があると思うが、避難所で生活をしている被災者は生活の場であります。
一般ボランティアは体験型といえることから遊びではなく生活を最優先と考えたです。
文責:
災害OUT・SIDE
正村圭史郎
E-mail saigaioutside@yahoo.co.jp
「遠距離避難」避難所と仮設住宅の運営を考える
避難所といえば救援物資の仕分けや被災者への救援活動に多くのボランティアが
活動を行うイメージですが、
この「遠距離避難」の避難所では、一般ボランティアの活動参加は無いものとします。
自治会組織を立ち上げていただき、掃除や食事の世話などは自治会の会合などで被災者の
皆さんが決めていただき行ってもらう。
避難所の管理責任は当該避難所として使用している体育館などの職員が担当するが、
避難者からも管理責任者から消灯などの作業を担うこともあります。
物資の仕分けや搬入などの作業は、雇用対策の一環として被災者が担えば生活再建の
一つの行動といえます。
避難所の自治に関する活動は、被災者自らが担う事が重要です。
それ以外の作業は…
医師、看護師、介護士などの有資格ボランティアが活動を行います。
避難所での運営には、自治会内で話し合い、自治会役員などと滋賀県や当該避難所の市町関係者
が参加をし会議を行う。
仮設住宅へは、避難所で構築された自治会組織の班単位で入居することが望ましいです。
個室内での新たなコミュニティー作りには個人差があります。また、コミュニティー作りに失敗
して塞込んだ場合に仮設内では発見が遅れることになります。
避難所や仮設住宅に一般ボランティアが参加したいと申し出や学生(生徒)などからも
希望者があると思うが、避難所で生活をしている被災者は生活の場であります。
一般ボランティアは体験型といえることから遊びではなく生活を最優先と考えたです。
文責:
災害OUT・SIDE
正村圭史郎
E-mail saigaioutside@yahoo.co.jp
Posted by すきまかぜ編集部 at
02:51
│Comments(0)
2011年03月20日
【地震】東北地方太平洋沖地震7-4
2011年3月20日
「遠距離避難」の避難所と仮設住宅を考える
避難所へは出来るだけ地区単位での避難がよい、バラバラの避難であっても避難所に入れば
自治会組織を立ち上げてもらい、避難所運営の大部分を自治会が行うことが望ましいです。
避難所となる場所には通常の災害指定避難所の枠にハメない方がよい
避難所といえば学校の体育館とイメージがわきますが、絶対に小中学校などの施設に避難所は
設けてはいけないと思います。
避難所になった場合に、体育館だけを使うのではなく、施設全部を使うことになります。
子供たちの保護者の理解を得ることが大変です。
避難所は体育館や会議室などが使用されます。大きさと収用人数は…
(例)
大体育館(バスケットボール1面、バレーボール2面)
被災者数=300人
小体育館(バレーボール1面)
被災者数=150人
大会議室(長テーブル20、椅子80)
被災者数=100人
中会議室(長テーブル10、椅子40)
被災者数=60人
小会議室(長テーブル5、椅子20)
被災者数=30人
自治会組織(班)は30人位で一班と考えて、大体育館なら10班位の自治会組織を立ち上げる
自治会には、正副3~4名以下、各班長と班の副も2人程が当たる。
仮設住宅を考えてみる
仮設住宅は法律で決まった大きさがあります。約30㎡以下です。仮設期間は2年、災害時の
場合は2年ごとに更新あり。
(例)
彦根市金亀公園運動施設のゲートボール場
広さが1270㎡あります。この広さの場合は、約30戸の仮設住宅を建設できます。
しかし、小中学校などのグランドや児童公園などへは設置してはいけません
避難所同様に問題が多いです。公園などの施設に仮設住宅を設置すると近隣住民の憩いの場を
失うことになります。
仮設住宅に入居する際にも避難所で構築された自治会組織単位での移動などとが望ましいです。
この避難所と仮設住宅の期間は、来年春頃までと考えています。
仮設住宅は2年間ですが…
休眠の火力発電所などが再開し計画停電が解消されれば、福島県内や関東の東京電力エリア
へ移転できます。
避難所や仮設住宅での物資や備付備品(エアコンやテレビ)は福島県内の商工会などと連絡を
取って福島県内の業者を通じて揃えて貰えれば福島県内の商工業が少しは潤います。
文責:
災害OUT・SIDE
正村圭史郎
E-mail saigaioutside@yahoo.co.jp
Posted by すきまかぜ編集部 at
02:20
│Comments(0)
2011年03月20日
【地震】東北地方太平洋沖地震7-3
2011年3月20日
「遠距離避難」の滋賀県を考える
滋賀県を候補としましたが、滋賀県でも湖北・湖東・東近江の地域です。
その地域にはJR東海の新幹線米原駅があるからです。
米原~那須塩原(東北新幹線の駅)
約3時間40分
米原駅からは…
北陸線で湖北地域に…
東海道線で彦根や近江八幡へ…
近江鉄道で八日市(東近江市)へ
アクセスが豊富にあることから米原駅の近郊を候補とさせていただきました。
朝に出れば昼前に福島県に到着、夕方に出れば夜には帰宅できる距離です。
他の候補も考えましたが、新幹線の駅が市街地の中心地にあることから駅の近隣に
避難所となる体育館や仮設住宅建設地となる広場がなく、通常の交通機関での移動が
困難な場所までいくことになります。
最大のポイントが関西電力エリアだという事です。
何それ?と思われますが電力会社を挟んだ避難が「遠距離避難」といえます。
東京電力や東北電力エリア内での避難の場合には計画停電が実施された場合に避難所や仮設住宅
は停電実施外となるでしょう。
しかし、近隣住宅地では計画停電として一日3時間の停電が行われます。
昨年同様に猛暑の夏になった場合、エアコンを利かせた仮設住宅と停電となった近隣住民との
間にかい離がうまれます。
近隣住民に気兼ねして仮設住宅の被災者が電気を切ってエアコンを止めると仮設住宅の室内温度は
過酷なモノになり熱中症の原因となります。
近隣住民も同様に3時間の計画停電時に熱中症で倒れる方が出るかもしれません。
文責:
災害OUT・SIDE
正村圭史郎
E-mail saigaioutside@yahoo.co.jp
Posted by すきまかぜ編集部 at
01:16
│Comments(0)